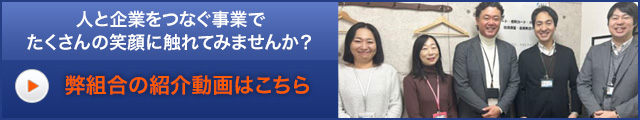コラム
【連載2】燃料の『暫定税率』、そろそろ“暫定”を終わりにしよう!(全3回)
第2回:燃料コストが直撃 ― 暫定税率が物流を圧迫する理由
日々自動車を使用する企業、特に運送業界にとって、燃料費は“命綱”です。トラックが1台動くごとに軽油が消費され、その価格は経営に直結します。暫定税率による上乗せは、軽油価格を常に高水準に保ち、業界にとって構造的なコスト増の要因となっています。
特に中小の運送会社では、取引先との契約構造上、燃料高騰分を運賃に十分転嫁できないケースが多く、「走れば走るほど赤字になる」という声が珍しくありません。
さらに、燃料費が増えれば、ドライバーの給与改善、安全投資、車両更新など、本来必要な分野に資金を回せなくなります。結果として、人手不足・車両老朽化・安全リスク増という悪循環が生まれています。このまま物流現場の諸改善が進まなければ、2030年には全国で荷物全体の3割超を運べなくなる可能性も出てくると言われています。しいては物流品質の地域格差が生じる可能性も考えられています。
また、近年の脱炭素化やEVトラックの開発など、業界の構造転換が進む中で、暫定税率が“時代遅れの負担”としてイノベーションのブレーキになっている面もあります。
つまり、暫定税率は単なる税の問題ではなく、日本の物流の持続可能性を左右する制度的課題なのです。
👉 最終回(11月21日)では、政府の最新動向と廃止に向けた議論、そして業界として今後どう動くべきかを見ていきます。