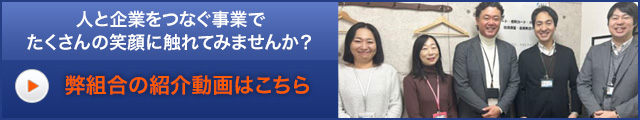コラム
【連載1】燃料の『暫定税率』、そろそろ“暫定”を終わりにしよう!(全3回)
─ 50年続く「期間限定税」が、物流の未来を左右する
第1回:「暫定税率」って何? ― 50年続く“期間限定税”の正体
ガソリンや軽油の価格に含まれている「暫定税率」。名前のとおり“期間限定の税金”ですが、その歴史は意外に古く、1974年(昭和49年)にさかのぼります。
当時はオイルショックで財源が不足し、「道路整備のため」として導入されたのが始まり。本来は一時的な措置でしたが、その後も延長が繰り返され、なんと50年近くも続いているのが現状です。
いまもガソリン1リットルあたり約25円、軽油で約17円が上乗せされています。つまり、私たちは給油のたびに“期間限定のはずだった税金”を払い続けているのです。
10月時点での全国平均価格はレギュラーが158.6円(税抜)、軽油が143.5円(税抜)となっています。
時代が変わり、道路が整備された今、「本当に必要な負担なのか?」という疑問の声が再び高まっています。
給油価格が上昇し始めた数年前から暫定税率廃止に向けた議論は起きていましたが実現はせず・・・ただ今年10月に誕生した高市政権下での議論が加速している状況です。
👉 次回(11月19日予定)は、暫定税率が運送・物流業界にどんな影響を与えてきたのかを掘り下げます。