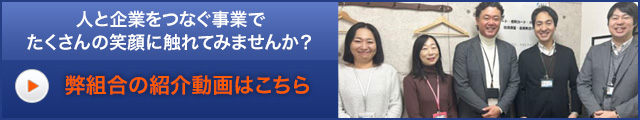BCP策定委員会 社内発表
先日、BCP(事業継続計画)策定委員会の社内発表を弊組合(SLC)オフィスで実施いたしました。
BCP(Business Continuity Plan)とは、自然災害や感染症、サイバー攻撃などの緊急事態に備え、事業資産の損害を最小限に抑えつつ、中核事業の継続または早期復旧を可能にする計画です。
SLCでBCPが始動したのは2020年。新型コロナウイルスの感染拡大により、社会や経済、日常生活のあらゆる側面が劇的に変化した年でした。
新型コロナウイルスはサプライチェーンや交通インフラにも大きな影響を与えました。それは、日常的に業務で車両を使う数多くの中小企業様にご加入いただいている弊組合にとっても例外ではありません。中小企業は大企業と比べて災害時の打撃が致命傷になりやすいということを踏まえ、むしろ率先して取り組んでいく必要があるのではないかと考えたことがきっかけでした。
そうした背景から、現在は毎年2か月に1回のペースで、同委員会を開催しています。
今年度は「策定したBCPを社内へ周知する」をテーマに活動しています。


当日は下記の議題に沿って発表が行われました。
①BCPとは
BCP策定の目的やBCPが必要とされる背景に触れ、防災計画との違いという観点から考えました。
BCPは事業継続、防災は人命・資産の保護が主な目的となっており、各々の計画を策定する上で、身の回りに潜むリスクを整理することから始めました。
BCPが想定するリスクは防災計画より広範に渡っています。物流・運送業界で例えると、物流拠点の分散配置から災害時の配送ルートの選定、代替輸送手段の確保から、サプライチェーンの維持や顧客対応まで、重要業務を止めずに維持・復旧することに焦点を当てました。
②自社のBCP(事業継続計画書)
私たちを取り巻く環境に潜むリスクについて、ハード、ソフトの両面から整理しました。その上で、組合が機能不全に陥った場合に想定される影響を題材に、フレームワークを行いました。
まず、弊組合のオフィスは東京都豊島区にあり、本社機能が集中していること。営業活動はシステムに依存しているため、被災時はバックアップが必要になる可能性があります。社員も出社できるかどうかわかりません。そんな状況下において、どうしたら主たる事業を継続できるのか意見を募りました。
⇒代替手段・拠点の確保
⇒災害発生時でも事業用車両は動く⇒ETCや給油といった事業が必要になる?
⇒緊急連絡網を作成
⇒出社せずとも、ポータブル端末で仕事ができるようにする
⇒申請関係は一時的に紙ベースで運用する …など
③事業特性を踏まえたBCPの再設計
メディアで取り上げられるなどして急に来客が増えたラーメン店を事例に、組合の事業に対する需要が急増したケースを想定してBCPの再設計を試みました。
2グループに分かれ、必ずしも自分たちのマンパワーだけで対処しようとしないことに留意しつつ事前準備や対策方法について考えてみたものの、最初はなかなか具体的なアイデアが浮かびませんでした。
そこで、身近なラーメン店の事例に手掛かりを求めました。ラーメン店であれば値段を上げる、入れ替え制にする、メニューや席数を制限するといったようなことを組合活動に置き換え、自分たちにできることから考えました。
会議終了後は、BCPの一環として常備しているアルファ米を近所の飲食店からテイクアウトしたおかずと一緒にいただきました。アルファ米は梅がゆやチキンライスなど種類が豊富で、おかずに合わせて水の量でお米の固さを調整できるところがよかったです。また、社員全員で同じものを食べたことでコミュニケーションも図れて有意義な時間となりました。

今後も社内外の知見を集積し、平時だけでなく非常時でも皆様に安心してサービスをご利用いただける組合になれるよう精進いたします。